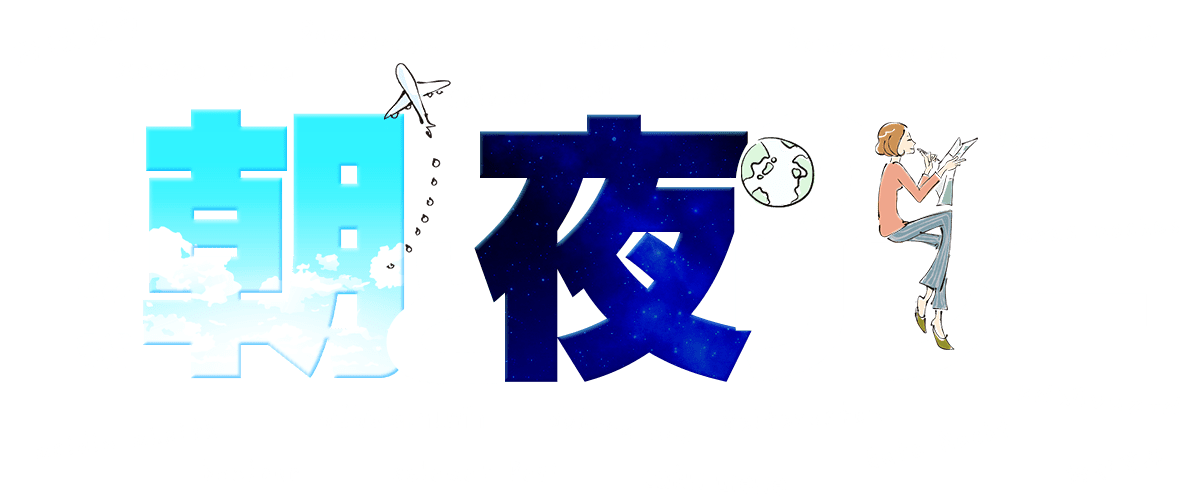世界一長い山脈として知られるアンデス山脈。
今回は、そんなアンデス山脈の家の特徴や高地での生活、そしてそれが日本とどう異なるのかについて紹介します。
アンデス山脈とは
アンデス山脈は、南米大陸の西側を南北に走る、世界で最も長い山脈です。
その全長は約7,500kmに及び、ベネズエラからチリ、アルゼンチンまでの7カ国にまたがっています。
アンデス山脈は、地球上で最も高い山々の一部を含んでおり、その中でもアコンカグア山は標高6,960mで、アンデス山脈の最高峰として知られています。
アンデス山脈は、その地形の多様性により様々な気候帯を持っています。
北部のベネズエラやコロンビアでは、熱帯雨林が広がり、多湿な気候が特徴です。
中央部のエクアドル、ペルー、ボリビアでは、乾季と雨季の変化があり、高地の草原や砂漠が見られます。
南部のチリとアルゼンチンにかけては、乾燥した高原や氷河が存在します。
この壮大な山脈は、多くの生物の生息地であり多様な文化が育まれてきました。
インカ帝国の発展にも大きく寄与し、今日でも多くの先住民族が伝統的な生活を営んでいます。
アンデス山脈は、その自然の美しさとともに、人々の生活や文化に深く根ざした、地球上で唯一無二の場所と言えるでしょう。
アンデス山脈の家の特徴
アンデス山脈の家々は、その地で手に入る素材を使い家を建てています。
そのため、北部と南部で気候が変わりますが基本的には石や日干しレンガで家を作っています。
場所によっては、屋根の素材が藁やトタンで覆われた家もあります。
昼夜の気温差が大きい高地の気候では-20℃になることもあり、寒い日には家畜の糞を薪がわりにして暖をとります。
そのため、家の中では煙が充満し、気管支系の健康被害にあいやすいです。
しかし、近年ではそんなアンデスの住人を支援するために活動をおこなう団体もあり、ソーラーパネルを取り付けた家や、断熱材を装備した家なども少しずつ増え、変わってきています。
高地での暮らしは自然との共生
アンデスの人々は、標高2000mから4000mの間で農業を行い、トウモロコシやジャガイモを栽培しています。
その他には、日本でも人気のリャマやアルパカなどのラクダ科の動物4種類が生息しており、リャマやアルパカを放牧しています。
リャマやアルパカは、荷物運搬や毛皮を提供する重要な役割を果たしています。
アンデス山脈に生息するラクダ科の動物
- アルパカは、その上質な毛皮で有名で、標高3000~4000mの乾燥した高原地帯に生息しています。
- リャマは、人に懐く性質があり、主に荷物運搬や毛皮の供給源として利用されています。
- ビクーニャは、標高4000~4500mに生息しており、毛皮は最高級品とされ非常に警戒心が強く絶滅危惧種です。
- グアナコは、標高0~2000mのパタゴニアやチリ北部の低地に適応し、現在はパイネ国立公園で見ることができます。
その他にも、チチカカ湖に生息するチチカカ水ガエルやペットとしてもお馴染みのチンチラなど、多岐にわたる種類の生き物が生息しています。
日本と違うアンデス山脈に暮らす人々の魅力
アンデスのファッションと言えば、ポンチョです。
ポンチョは簡単な作りですが、とても機能的です。
アルパカの毛で作られたポンチョは、袖がない洋服のような仕様ですがこれは強風や寒さを凌ぐためです。
また暑い時にすぐさま脱げる仕様で、脱着にとても便利です。
色鮮やかで機能的なポンチョは、一時期日本でもブームになりましたよね。
その他、帽子もよくかぶっています。
これはオシャレのためではなく、高地の強い日差しを防ぐ対策としてかぶっています。
また、有名どころで言うとペルーのマチュピチュにはインカ帝国の遺跡があります。
標高2,400mの断崖絶壁に作られた文明的な建築物や生活の跡を残す大都市帝国は、日本でいうと戦国時代あたりの人々の暮らしを現代に感じることができます。
星を読み、太陽を読み自然と共存したながらも最先端の技術が育まれたインカ帝国は、ロマンを求めて今も訪れる人が絶ちません。
まとめ
アンデス山脈の家と暮らしは、その地域特有の自然環境と密接に結びついています。
日本とは異なるこれらの生活様式は、文化の多様性と人々の適応力の素晴らしさを教えてくれます。
私たちは、異なる文化を理解し、尊重することでより豊かな世界観を持つことができるのです。
それでは、次回も世界の家の多様性をお届けします。
広告